🍼 はじめに:育休中のパパは何をして、どう過ごしてる?
一昔前に比べたら、育休を取るパパは確実に増えていると感じます。しかし、実際に育児を担うパパもいれば、育児に関わらないパパもいて、『取るだけ育休』『名ばかり育休』といった言葉もあります。
これから育休を取るパパや育休が始まったばかりのパパは、名ばかりではなく充実した育休にしたいと考えているはず。そんなパパも、『育休中、どう過ごせばいい?』『家事や育児の分担は?』と悩むことも多いのでは?
そんなパパたちのために、この記事では 「ペンギンパパが実際に育休中に過ごした1日」 をリアルなスケジュールとともに紹介! 事前の準備・計画がどれほど大切か、育児を有意義にするコツ も合わせて解説します!
- 育休中のパパの1日のスケジュール
- 充実した育休を過ごすために必要な準備
- 育休を取得するパパに向けたアドバイス
僕が実際に育休中に過ごしていたスケジュールや、育休中にパパがやっておきたいことも解説するよ!
🕛 育休中のパパの1日の流れとポイント
まずは早速、ペンギンパパが実際に育休をどう過ごしていたのかご紹介します。
朝|ママのケアと赤ちゃんのサポートが最優先!
朝起きたらまずはママの体調と赤ちゃんの昨晩の様子をチェック。ママが体調不良なら、母乳予定をミルクに変更して休ませたりと、その日の過ごし方を調整します。
- ママの体調確認
- 赤ちゃんの昨晩の様子を確認(寝ている間の異常の有無や、変化など)
- 赤ちゃんの朝一のオムツ替え・保湿・着替えを担当
特に問題なければ、朝一のおむつ替えと保湿を私が担当していました!
たまに朝がしんどいときがあって、そんな時に少しでも安心して休めると、とても助かったわ。
午前中|赤ちゃんの外気浴タイム!寝ている間は家事や趣味に没頭
特に新生児の頃はほんの5分程度でしたが、1ヶ月、2ヶ月と成長に合わせて午前中に赤ちゃんの外気浴や散歩をしていました。午前中の日光を少し浴びることで、赤ちゃんも1日の生活リズムがだんだんと整っていきますよ。
- 授乳前にミルクの準備(すぐ対応できるように)
- 哺乳瓶の消毒や、洗い物をまとめて実施
- 赤ちゃんが寝ている間に読書やゲームなどの趣味時間をエンジョイ
赤ちゃんが寝ている間に哺乳瓶の消毒や洗い物を済ませた後、自由時間として読書やゲームを楽しんでいました。
午後|家族でお出かけランチや育児講座への参加
午後は家族での外出や、市区町村の育児講座への参加が多い時間帯でした
午後も引き続き、育児・家事をこなしつつ、赤ちゃんが寝ている時間は自由に過ごします。
徐々に赤ちゃんと安心して外出できるようになってからは、妻も一緒に家族でランチやティータイムに少し外食したり、スーパーへの買い出しに一緒に行ったりしていました。市区町村の育児相談会などにも、午後の早い時間に参加することが多かったです。
- 午後はママの休息時間。ママが別部屋で寝ている間に、パパが主担当で赤ちゃんのお世話。
- 絵本の読み聞かせやベビーマッサージなどで赤ちゃんと触れ合う
- ときどき、市区町村の育児講座や相談会に参加し、同期のパパママと交流
夜|お風呂・寝かしつけ&パパのリラックスタイム
夜は赤ちゃんのルーティンを意識して、特に気を使っていました。お風呂→その日最後の授乳→寝かしつけ、というルーティンを定着させることで、生後2ヶ月ごろから夜は朝までまとめて寝てくれるようになりましたよ!
- お風呂はパパの担当!その日最後の授乳前にお風呂に入れ、スムーズな寝かしつけをサポート
- お風呂から出て授乳が終わったら部屋を暗くして寝る環境を整える
- 泣いたらパパとママが交代で抱っこ。
- 赤ちゃんが寝たらママと一日の振り返り、パパの自由時間&就寝
ルーティンが定着してからは21~22時以降が自由時間って感じでした!
👨👩👦 充実した育休のために必要な事前準備
私が充実した育休を過ごせたのは、事前に妻と相談して多くの「準備」「計画」があったからです。
育休を充実させるために必要な事前の準備は大きく分けて「育児体制の準備」と「育休中にやりたいことの整理」の2つです。まずは「育児体制の準備」について解説します。
📌 育児体制・グッズ・スペースの準備
赤ちゃんが産まれて育児が始まる前に、「家事育児の分担」「育児グッズ・育児スペースの準備」「親の休憩スペースの準備」の3つです。それぞれ、ポイントと合わせて解説します。
家事育児の分担
まずはなんと言っても家事育児の分担です。これを事前に決めていないと、「私ばかり赤ちゃんのお世話をしている」「夫(妻)は何もしてくれていない」と感じてしまいやすいです。きちんと話し合って事前に分担を決めましょう!
分担を決めるときのポイントは家事と育児を分けて考えることと、それぞれの得意分野を担当することです。
例として、我が家では家事と育児は下記のように分担していました。
- パパの担当:掃除・料理
- ママの担当:洗濯・買い出し
我が家では家事は普段からお互いが得意なものを担当していたので、それをそのまま継続しました。
- パパの担当:日中のお世話+お風呂
- ママの担当:夜間のお世話+ファッション担当
赤ちゃんのお世話については、話し合った結果タスク毎ではなく、時間帯を区切って分担することに決めました。また赤ちゃんにパパにも懐いてもらうためお風呂だけは私が担当で、赤ちゃんのファッション担当(服の買い出しや、着る服の選定)はセンスのある妻が担当としました!


1つ注意点として、実際に育児が始まると事前の想定とは変わることもあります。
思ったより母乳が出る・出ない、赤ちゃんが夜間は寝ないのに昼はずっと寝ているなど、事前に決めた担当のどちらかに負担が偏ってしまうようであれば柔軟に分担を見直しましょう。
育児グッズの準備
次に育児グッズですが、赤ちゃんをお迎えするのに必須のグッズはお世話スペースと併せて事前準備しておくと良いです。赤ちゃんの肌着やタオル、寝具、哺乳瓶や消毒器具などは初日から必須です。
プレママ・プレパパ向けの育児雑誌などに、産まれる時期別の「必要なもの一覧」が載っていることが多いので参考にして揃えるのがおすすめです。私の経験から、下記2点については補足としてアドバイスします。
- 安物でいいので肌着は多めにあると安心&楽!10枚くらいあっても良し!
→ 新生児はすぐに大きくなって着れなくなってしまうため、一般的には5~6枚と紹介されていることが多いです。しかし、これは毎日洗濯をする前提での枚数だと思ってください。吐き戻しやおむつ汚れなどで服を汚すことが多いので1日に2〜3着使う日もあります。10枚あると2〜3日に一度まとめて選択すれば良いので楽になりますよ。 - ミルク育児がメインなら、哺乳瓶は最低3つは用意するのがおすすめ!
→ 哺乳瓶は消毒前に乳首や瓶を洗う必要があり、結構な手間がかかります。これを都度都度やるのは大変なので、哺乳瓶も3つは用意しておいて、3つをまとめて消毒すると楽になりますよ。
※我が家で使っている消毒器具が哺乳瓶3つまで入るため最低3つと書きましたが、より多くをまとめて洗える消毒器具を利用する場合はより多くてもいいかもしれません。
育児スペースの準備
次に大事なのが、赤ちゃんのお世話に必要なスペースの準備です。これを決めておくことで、病院から退院後スムーズに育児を開始することができます。
赤ちゃんのお世話スペースは、一般的には下記の条件を満たすスペースを用意する必要があります。
- 赤ちゃんを寝かせておくのに十分なスペース
- 空調管理が可能(エアコンで室温管理が可能)なスペース
- 赤ちゃんの安全が確保できるスペース(物が落ちてこない、ペットが触れない、等)
我が家の場合はリビングの一部にプレイマットを敷いてお世話スペースとしていました。プレイマットの周辺は全て片付けて危険物がないようにし、赤ちゃんの寝具もプレイマットの上に直置きです。
準備しようと思うと意外に考えることが多いので、事前に準備しておくのが吉です。特に、赤ちゃんを寝かせられる安全な場所を決めて準備しておかないと、赤ちゃんも危険ですし、親も気を遣ってストレスを感じ続けることになってしまいます。自分が安心して過ごすためにも必ず準備しましょう。
親の休憩スペースの準備
赤ちゃんのお世話スペースと合わせて、事前に確認したいのが親の休憩スペースの準備です。
育休期間中は夫婦で分担して育児をしていくわけですが、自分が担当していない時間に睡眠を取ったり休憩をすることになります。赤ちゃんは2〜3時間毎に起きては泣くので、赤ちゃんと同じ部屋だとゆっくり休めないのです。
そのため、可能であれば赤ちゃんの泣き声が気にならない別の部屋で休憩ができるように、環境を整えておくのがおすすめです。どうしても同じ部屋しか使えない場合は簡易的でもいいので仕切りを設けて、照明も分けれるようにするといいかもしれません。
📌 育休中にやりたいことの整理
次に育休中にやりたいことの整理です。これは育児の観点でやっておきたいことと、パパの希望でやりたいこと、どちらも考えておくのがおすすめです。
育児でやりたいことを書き出しておくのは、育児への気持ちも前向きになりますし、分担を考える時の参考にもなります。例えば、下記のようなことです。
- 赤ちゃんの初めてのお風呂は担当したい!
- 赤ちゃんを連れて、〇〇へ出かけたい!
- 赤ちゃんを両親に合わせたい!
- 赤ちゃんには好きなアーティストの曲を聞かせたい!など
一方で、育休というのは長期間、仕事から離れられる貴重な機会でもあります。普段は仕事で忙しくてできないようなことにも取り組むいい機会です。例えば、下記のようなことです。
- 積読になっていた本を読み切りたい!
- 英語や仕事の資格など、スキルアップの勉強時間をとりたい!
- 健康のために運動習慣を身に付けたい
もちろん、育児と両立することが前提になりますが、やりたいことを整理しておくことで妻にも相談や調整がしやすくなります。どうしても両立が難しいものは、別の機会を検討するのも一つの選択肢です。
💡 パパへのアドバイス|育休中にやっておきたいこと
最後に、私の育休経験を元に、全国のパパさんに検討してほしい育休中にやっておきたいことの紹介です!
これは育児を始める前に知っておきたかったこと、と言い換えてもいいです。育児が始まる前は意外と気づかなかった、あるいは考えつかなかったことなので是非参考にしてください。
- プロカメラマンやカメラスタジオによる写真撮影
現代ではスマホで撮れば良いやとなりがちですが、赤ちゃんの成長は本当にあっという間。特に新生児期の「ニューボーンフォト」や「お宮参り」「お食い初め」といった早い時期のイベントは事前に計画していないとあっという間に時期が過ぎてしまいます。少し値段ははりますが、我が家ではニューボーンフォトが宝物になっています。 - 赤ちゃんを連れて、両親や祖父母に会いに行く
家族が離れて住んでいると、なかなか会う機会ってないですよね。育休中は空いている時期に移動することもできるので、赤ちゃんと外出可能になったら是非会う機会を作ってあげてください。孫はやはり可愛いようで、とても喜んでもらえますよ。 - 今後の人生設計を考える
実際に赤ちゃんが産まれて育児を開始すると、価値観が変わることもあると思います。私の場合は、これからは仕事ではなく娘との時間を大切にしたいと考えるようになりました。また子供が産まれたことによって、家が手狭になるなど物理的な変化もあります。「家の広さを見直す」「転職や働き方を考える」など、育休中に考える時間をとって、これからの人生設計をしてみると、より充実した育休になります。
育休中のパパは「計画的かつ柔軟に」動くのが大事!
育休は、赤ちゃんとじっくり向き合い、夫婦で家族の土台を築く貴重な時間です。
そのために、「事前の準備」「家事・育児の分担」「育休中にやりたいことの整理」 をしておくことで、スムーズに育児が進み、より充実した育休を過ごせるでしょう。
- 充実した育休を過ごすためには事前の準備と計画が大切
- 家事・育児の分担を話し合い、柔軟に調整できる体制を作る
- 赤ちゃんの育児グッズ・お世話スペース・親の休憩スペースを準備する
- 育休中にやりたいことを整理し、パートナーと共有する
- 育休中におすすめするアクション
- プロフェッショナルに依頼して赤ちゃんの写真を撮ってもらう
- 赤ちゃんを連れて両親や祖父母に会いに行く
- 育休後も見据えた、今後の働き方や家族のライフスタイルを考える
計画と柔軟性を大切にしながら、育児を楽しもう!

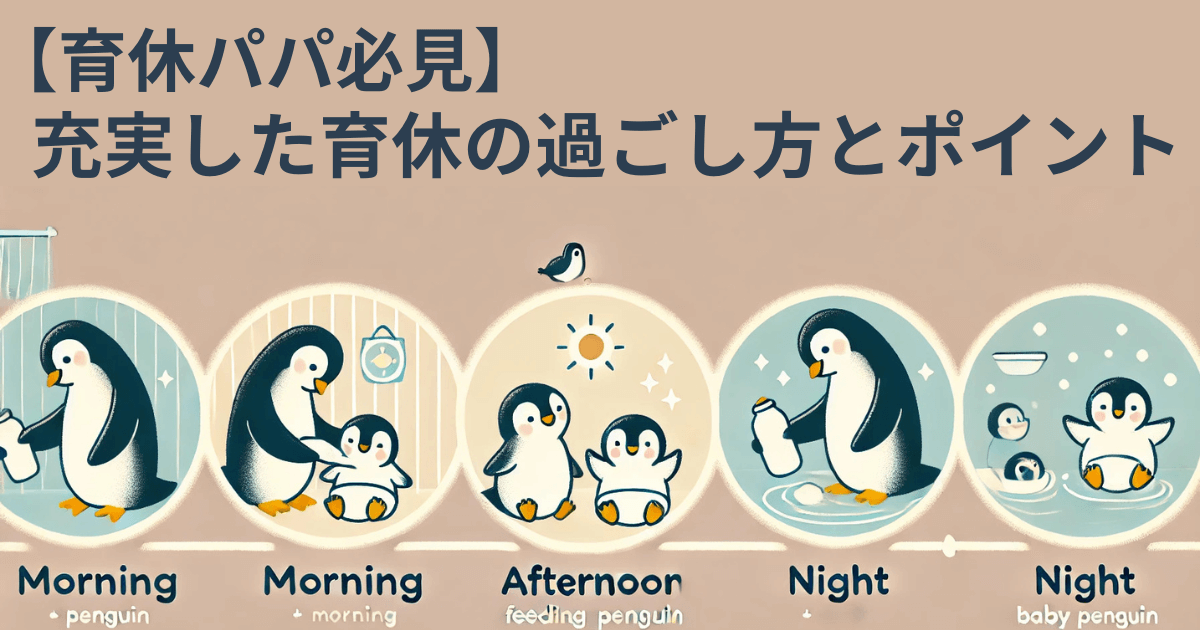





コメント